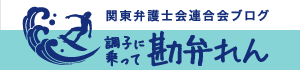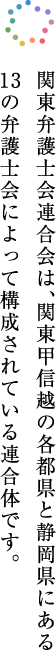
「関弁連がゆく」(「わたしと司法」改め)
従前「わたしと司法」と題しインタビュー記事を掲載しておりましたが,このたび司法の枠にとらわれず,様々な分野で活躍される方の人となり,お考え等を伺うために,会報広報委員会が色々な場所へ出向くという新企画「関弁連がゆく」を始めることとなりました。

俳優
正名 僕蔵さん
- とき
- 平成31年2月25日
- ところ
- 日本テレビ生田スタジオ
- インタビュアー
- 会報広報委員会委員長 鈴木大輔
今回の「関弁連がゆく」は正名僕蔵さんです。
現在日本テレビ系列で放送中のドラマ「イノセンス~冤罪弁護士~」に弁護士役(役名:登別次郎)でご出演中の正名さんは,映画「それでもボクはやってない」では裁判官役,ドラマ「HERO」では検察事務官役をなされる等,今や映画・ドラマには欠かせない名バイプレイヤーです。
今回は,正名さんに弁護士役を含めた法曹関係者を演じられての感想について伺って参りました。
― はじめに,正名さんは,青山学院大学文学部のご卒業とのことですが,俳優を目指されたきっかけについてお話をお聞かせいただけますか。
正名さん
大学3年のときに,演劇好きの友達から,大人計画という劇団が面白いから観に行かないかって誘われたんです。その舞台に,演技が面白くてとても可愛らしい女優さんが出ていらしたんですね。
で,劇場で渡されたチラシの束の中に,大人計画が今度オーディションをしますという募集のチラシが入っていて,確かオーディション料が3000円だったと思うんですけど,このオーディションに行けば,あの女優さんに会えるかもと思って,受けに行ったんです。
そうしましたら,実際オーディション会場にはいらっしゃらなくて,当時私は演劇については全くの素人だったんで気づかなかったんですが,その方は正式な劇団員ではなくて,その公演だけの客演という,いわゆるゲストの方だったんです。
「なんだ,いないじゃん」と思って,がっくりきながらも,とりあえずオーディションを受けたわけですよ。色々と,音楽に合わせて踊ってくださいとか風船を膨らましてくださいとか腕立て伏せをしてくださいとか,それから男女ペアになってコントをさせられたりしました。
終わって,3000円無駄にしたなぁと思いながらすごすご帰ったんですけど,後日,合格しましたという連絡がきまして。で,ふと,考えたわけです,劇団にいればいつかはその女優さんに会えるかもしれない,と。そう思って「やらせていただきます」と返事をして劇団に入ったのが,この世界に入ったきっかけです。
ですから,動機が不純と言いますか,役者を目指してっていうのが入口ではなかったんですよね(笑)。
― その行動力がすごいですね,演劇の世界に入ることに対して躊躇はなかったのでしょうか。
正名さん
それはなかったですね。劇団に入ったのが,ちょうど大学3年と4年の間の春休みで,そろそろ就職活動をしなきゃいけないなという時期だったんですけど,どうも普通に定職に就くというのに抵抗があって,何か表現の仕事をしたいなあとはぼんやりと思っていたんです。
親には,「演劇に興味を持ったから,ちょっと何年かやってみたい」と言ってみたら,わりとすんなり認めてくれて,というのもありました。ちなみに,20人くらいがオーディションを受けて半分の10人が合格したんですが,これは劇団に入ってから分かったことなんですけど,大人計画の主宰の松尾スズキさんが素人を使って舞台を作りたいという思惑があったらしくて,選考の基準として「演劇未経験者」を採ったそうで。ですから,私がたまたま演劇未経験者だったから受かったというのが実際のところですね。
― めぐり合わせもあったんでしょうね。ちなみに,その後,その女優さんとはお会いできたんですか。
正名さん 結局3年かかりました(笑)。入団から3年後にその女優さんが舞台を観にいらして。もうその頃にはすでに私がその方に憧れて劇団に入ったということは向こうには伝わっていたんです。で,終演後の飲み会でついにお会いできたんですが・・・。開口一番「へぇ~君がその正名くんなんだ~!」と背中をバンバン叩かれまして。もう面喰っちゃって,あれ,舞台の印象とまるで違うぞ,こんなに豪快な人なんだぁ,と。つくづく,女優は舞台で化ける生き物なんだなぁと圧倒されっぱなしでした。お会いできたことはほんとに嬉しかったんですが,恋心みたいなものはあっけなく吹っ飛んじゃいましたね(笑)。
― 憧れの方にお会いできるまでの3年間,あるいは,その方にお会いできてからの劇団にいるモチベーションというのはどこにあったのでしょうか。やはり,演劇が楽しいというお気持ちがあったのでしょうか。
正名さん 主宰の松尾さんが描く世界が面白いなと思っていて,その世界にそばで触れられることは楽しかったんですけども,そもそもが,役者を目指すつもりはなかったので,そこは苦労しました。お芝居をするとダメ出しと言って,結構手厳しいことを言われるんですよね。松尾さんがわりと温度低めにズバッと本質を突くみたいな演出をされる方で,例えば,「僕はね,一応面白いセリフを書いてるんだけど,君はなんでそんなにつまらなくできるの?」みたいなことを言われるんです。私はもう平謝りですよね,すみません,もう一回お願いします,と。そんな調子で,5,6年はツラいツラいと思いながらやってて。でも,そうやって厳しいことを言われながら,じゃあ,どうすればいいんだろうと試行錯誤を繰り返しているうちに,徐々に松尾さんの要求に応えられるようになってきまして。そうなると,気持ちにも余裕が出てきて稽古をある程度楽しめるようになってきましたから,そこからはもう一直線に演劇の世界にのめり込んでいきましたね。
― 演劇の世界からドラマや映画の世界へはどのように繋がっていったのでしょうか。
正名さん 20代の前半はドラマや映画などの映像の仕事はほぼなくて,基本舞台がメインで,たまにCMのオーディションに行って,運よく受かって,みたいな感じでしたね。25歳過ぎたあたりから,所属している大人計画の認知度がどんどん上がってくるにつれて,私にもドラマや映画からお声を掛けていただけるようになりました。初の連続ドラマのレギュラーをいただいたのが,29歳のときで,実を言いますと,それが,ここ日本テレビの番組だったんです。そのときにチーフのADをされていたのが,今回の「イノセンス」のチーフディレクターの南雲聖一監督で。さらに日本テレビの連続ドラマのレギュラーをいただくのが,その初めていただいた番組から20年経って久しぶりに今回の「イノセンス」で,感慨深い気持ちで生田スタジオで撮影しています。続けているとこんなこともあるんだなぁと。もちろん,ゲストで呼んでいただいてちょこちょこは生田スタジオに来ていたんですけど,連続ドラマの方はなかなかご縁がなくて,20年経って,当時,右も左もわからない私を見ていた南雲さんがいらっしゃる現場に戻ってこられたのは,やはり感慨深いです。
― 今回の撮影が始まってから南雲さんから当時のお話はされたりとかはありましたか。
正名さん それが,ないんですよね(笑)。当時の私は相当やらかしていたと思うんですけど,そういう話は一切されないですね。私のことをもう一人前の役者として演出してくださるので,私もそれに応えようと現場では張り切ってやっております。
― ドラマや映画の作品へのご出演というのは,オーディションと事務所へのオファーとでは,どちらが多いのでしょうか。
正名さん 私は,ドラマに関してはオーディションを受けたことがないんですよ。事務所から,今回このお仕事が決まりましたと連絡を貰ってやる形ですね。映画ですと,たまにオーディションを受けたりしますが。
― 正名さんは個人的なイメージとして,法律関係のドラマによくご出演されているように思うのですが。
正名さん
そうですね。初めての連続ドラマのときは,研修医の役だったんですけど,わりとお堅い仕事といいますか制服モノの職業が多いです。病院関係,警察関係,それから法律関係,いわゆる専門用語をしっかりしゃべらなきゃいけない役柄ですね。テレビに出始めた20代に往年の「火曜サスペンス劇場」から始まり,二時間ドラマによく呼んでいただいているんですが,警察官,刑事,医者の役がほんとに多くて,何気に法律関係の役は30半ばを過ぎてからかもしれないですね。若手の刑事とか若手の医者はいても,若手の法律家っていう役柄が少なかったからなのかもしれませんが,ある年齢からぐーっと増えました。検察官もありましたし,裁判官もやらせていただいて。それこそ,10年ちょっと前になりますか,周防正行監督の「それでもボクはやってない」で裁判官をやらせていだたいて,そのときに,その映画が痴漢の冤罪事件を扱っていましたので,当時,実際に開かれていた痴漢事件の裁判をいくつか傍聴しに行きました。
で,裁判所に行った日は,目当ての裁判だけでなく,窃盗だったり覚醒剤所持だったり,他の案件の裁判も見て回ったんです。そのときにガッツリ裁判というものの現場を目の当たりにしました。
― 実際に,刑事裁判を傍聴されて,どのような印象をお持ちになったのでしょうか。
正名さん 一番の印象は,裁判官,検察官,そして弁護士,みなさんにとって「法廷」は日常なんだな,と感じました。やっぱり我々からすると非日常じゃないですか,でも,みなさんからすると日々淡々と遂行されている「日常」という感じがすごいあって。周防監督から「実際見に行って,どうでしたか?」と聞かれたときに「裁判官の方にとって,法廷は日常ってことなんですかね」と答えたら,監督が「そうなんですよ!そこなんですよ!」と大きくうなづかれていました。
― 確かに,法廷での弁護士と検察官と裁判官とのやり取りは,普段の日常会話では使わないような言葉で行われることはありますよね。「しかるべく」とか「差し支えです」とか。
正名さん そうですね。あの,次の日時を決めるときのやり取りが,ごくこく普通の会話として行われているのがとても新鮮でしたね。
― 正名さんは,すでに法曹三者全てのご経験があるわけですが,役作りの上で,法律家というカテゴリの中で,さらに「法曹三者」それぞれを演じ分けたり,何か意識をなさったことはありますか。
正名さん それはもちろんいただいた作品の世界観というのを第一に,どういう切り口で作られているかってことを優先はするんですけど,私個人の物差しといいますか,感じ方で言わせていただくと,裁判官と検察官はやはりお仲間でいらっしゃるのかなっていう感じはしています。双方とも公務員ですし,それに対して弁護士の方はちょっと仲良くはなれないだろうな,と。たまたま私,裁判を見学しに行ったときに,傍聴席に私しかいなくて15分くらいで終わったんです。被告人と弁護士は法廷を出て行かれて,残った裁判官と検察官が,うっかり私がいるのを忘れて談笑を始めたんです。検察官が「いやー裁判官,えらい早く終わりましたねー。次までどうされるんですか。」と和やかな感じに。で,ふと,私がまだ残って聞き耳を立てていることに気づいて「あっ」ってなって,慌てて「早くお出になってください」と追い出されまして。あのやり取りを見てしまうと,やっぱりそういう関係性なのかなって。なので,弁護士の方からするとアウェーという言い方も変ですけど,強い言葉を使うと「体制」というものに対して法律を武器に,立ち向かっていくっていう感覚がどこかにあります。
― 裁判所や検察庁は組織として大きいですから,弁護士が個人あるいは事務所単位で裁判官や検察官と戦うのはだいぶ難しいですよね。
正名さん ああ,やっぱりそうなんですね。ですから,裁判官役や検察官役をやるときは,何かそういうものに守られているというか,後ろ盾があるという感じのドッシリといいますか,なかなか簡単なことでは動じないぞっていうテンションになりますし,弁護士役をやるときは,どこか攻めの姿勢というか,大きな山に立ち向かっていくぞという気分で臨んでしまいますね。
― 今回のドラマでは,たまたま企業法務部門の弁護士という役柄ですが,その辺の立ち位置はどのように調整されて演じられたのでしょうか。
正名さん
ドラマでは,企業法務の業務を具体的に行っているシーンは残念ながら出て来ないんですよ。「イノセンス~冤罪弁護士~」というタイトルのとおり,「冤罪」つまり刑事事件の方に焦点を当てていますので。ただ,舞台となる保駿堂法律事務所はそれだけを取り扱っているわけではないよという,法律事務所の背景として,こういう人間もいるというポジションとしてやっています。実際私は,わざわざ刑事部門に赴いて色々茶々を入れたりという役柄なので,そういう意味では,刑事部門に行ってセリフを言うときは,アウェーでやってるという感じがどこかあるんですよね。私1人対刑事部門チームなわけですから,ちょっと気を張っていたりするところが正直あったりします。
そんな中で,今回助かっているのが,私が演じている「登別次郎」という役に関して,衣装合わせで選んでもらった衣装にずいぶん助けられている部分があります。外見から入ることで,なんかそういう人なんだろうなとキャラクターが見えてくる時があるんですよね。衣装だけでなく,ヘアースタイルでも助けられますし。ある舞台演出家が雑誌のインタビューで,「役者は,医者よりも医者らしく,弁護士よりも弁護士らしく見えればそれでいい」と仰っているのを読んだことがあって。もちろん内面を掘り下げることも大事なんでしょうけど,「らしく見えることが大事」というのを目にしたときに,なるほどなぁ,と妙に納得してしまったことがあります。ですから,今回のように具体的に企業法務のシーンがない分,役作りの手がかりとして外見から入ることで,登別という「弁護士」を作っていきましたね。
― その点においては,私個人の印象ですけど,法服を着て裁判官をやられているときには裁判官に見えますし,検察官バッジを付けて検察官をやられているときは検察官に,検察官に付いているときには検察事務官に見えますし,今日もこうやって弁護士バッジを付けているお姿も弁護士にしか見えません(笑)。法曹三者どの役をやられても,こういう人いそうだなぁって思って見ています。外見だけでなく,もちろん表現力による部分も含めてさすがだなあと感じさせていただいています。
正名さん 嬉しいです。ありがたいです。そういうお褒めの言葉を頂くために私は頑張ってきました(笑)。役作りに関して,さらに言わせていただくと,ドラマは自分一人で作るものではありませんから,まず,全体を見てくださっている監督がいて,その采配というのがありつつ,演者のみなさんがそれぞれ台本からインスパイアされたアイデアを持ち寄って,たとえばサッカーのフォーメーションのように,このポジションに入るなら私はこっちに回りますね,みたいな感覚で関係性を構築していく面もあるわけですね。その関係性から浮かび上がってくる個々のキャラクターの色合いも,大事にしたいと常々思っています。
― 先ほど,弁護士役を演じられる前提として,弁護士のイメージをお聞かせいただきましたが,弁護士役を演じられる前と後とで,弁護士に対するイメージの変化というものはありましたでしょうか。
正名さん
うーん,なんでしょうね,「弁護士」イコール「言葉で勝負する職業」というイメージはもともとありまして,実際に役で演じる時もそこを一番に注意してきましたし,ワイドショーだったりドキュメンタリーなどで本職の方々の佇まいや振る舞いを観察しても,やはりそのイメージは変わらないといいますか,むしろますますそう感じることが多くなっています。
冷静に,言葉でコミュニケーションをとることを最優先にしている感じがどうしてもするので,つい,弁護士っていうと基本言い負かされないよっていうテンションになるんですけど,今回の「イノセンス」でも,そういうテンションで臨もうとしたんです。企業法務だし,事務所内では稼ぎ頭という設定なので,刑事部門のお前らなんかには言い負かされないよっていう気分で入ったんですけど,監督の方から「ん?ちょっと違うぞ」とご指摘を受けまして(笑)。
「登別次郎」という役にとって「保駿堂法律事務所」はホームグラウンドなので,「刑事部門」というアウェーに行っているとはいえ,大きく見ればホームなわけです。ですから,外で弁護士業務を行っているときは,さぞかし「攻めの登別」としてバリバリ仕事をこなしているんでしょうけど,事務所内ではどこか抜けているといいますかスキがあるといいますか,「ヘタレの登別」として言葉巧みな弁護士像にはこだわらなくなってきました(笑)。
― 貴重なお話をありがとうございました(笑)。正名さんの今後のご活躍をお祈りいたしております。
正名さん ありがとうございます。