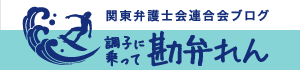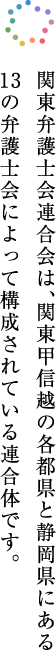
「関弁連がゆく」(「わたしと司法」改め)
従前「わたしと司法」と題しインタビュー記事を掲載しておりましたが,このたび司法の枠にとらわれず,様々な分野で活躍される方の人となり,お考え等を伺うために,会報広報委員会が色々な場所へ出向くという新企画「関弁連がゆく」を始めることとなりました。

俳優
髙嶋 政宏さん
- とき
- 2022年10月27日
- ところ
- フジテレビ本社
- インタビュアー
- 会報広報委員会委員 西岡毅
今回の「関弁連がゆく」は、俳優の髙嶋政宏さんです。
髙嶋さんはこれまで多数の作品に出演されていますが、最近では、フジテレビ系列にて放送されていた連続ドラマ「親愛なる僕へ殺意をこめて」(2022年10月~11月)で、警視庁の管理官役を熱演されていました。
元々は弁護士を目指していたという髙嶋さんに、俳優になるきっかけ・覚悟、撮影の裏話、役作り等についてお話を伺ってまいりました。
― 本日はよろしくお願いします。
髙嶋さん よろしくお願いします。今日は弁護士の方がいらっしゃってお話できるということで、楽しみにしていました。僕は、成城大学法学部法律学科の出身で、実は弁護士を目指していたんですよ。
― 何か、弁護士を目指すきっかけがあったんでしょうか。
髙嶋さん 父親から、将来は人を助ける仕事、例えば、医者や弁護士を目指すようにと言われていました。医学部は無理だろうと思いましたが、法学部に入学できましたので、入学直後のフレッシュマンキャンプの進路相談で「弁護士になりたい」と教授に言ったところ、鼻で笑われて、「なれるわけないだろう。俺がなれないんだから。」と言われてしまいまして(笑)。僕は、元々、中学生からベースを弾いていたので、その夜に大学のバンド演奏を聴きにいき、先輩達のロックの新入生歓迎ライブを見ていたら泣けてきて、「弁護士は無理だ、やっぱりバンドしかない。」と、入学初日にあきらめてしまいました。
― 素早いご決断だったんですね。ベースは、いつから、どんなジャンルをやっていらっしゃったんですか。
髙嶋さん 中3の文化祭からでした。当時は、ハードロックバンドのコピーをやっていて、高校、大学では、ディスコのパーティーバンドをやったり、ビジーフォー(*グッチ裕三さん、モト冬樹さんらが所属していたコミックバンド)の前座もやっていました。余談なんですが、俳優になった後、クワイエット・ライオットのドラムスの方とお話しする機会があって、「僕は、今、俳優やってますが、元ベーシストなんです。」と伝えたところ、「ミュージシャンに『元』というのはない。今でもベーシストだよ。」と言われたのは印象的でした。
― 本格的に音楽活動されていたんですね。では、何がきっかけで俳優業に方向転換されたんですか。ご家族の影響でしょうか。
髙嶋さん 大学3年の時に、相米慎二監督の「光る女」という作品の公募があって、父から応募を勧められました。身長185cmの熊のような男という条件だったんです。当時の僕はアメフトもやっていて身体が大きかったですから、オーディションとして相米慎二監督に会いに行ったんですが、喫茶店で会った瞬間、話をする前に、「華奢だから駄目だ。縁があったらまた会おう。」と言われてしまいました。その帰り、駅まで行くときに震えがきたんですよ。「もし、今受かってたら、映画に出てたのか」と。終わってから緊張がきましたね。
― それがきっかけで俳優の勉強を開始されたんですか。
髙嶋さん いえ、全然。ただ、そのオーディションの話を今の所属事務所の東宝芸能が聞きつけて、「俳優やる気あるのか。じゃあ、斉藤由貴主演の『トットチャンネル』のオーディションがあるから、うちの新人俳優として受けに行け」と。それで、アメフト試合後にチームジャンパーで東宝撮影所にオーディションに行きました。面接では、「みんなジャケットなのにジャンパーで来て面白いな」なんて話をされたくらいでしたが、結果的に受かりました。
― 手応えはあったんですか。
髙嶋さん 全くなかったですよ。「おもろいやないか」というだけで決まったんだと思います。ある時、家に帰ったら、父と、従姉妹の高嶋ちさ子の父、つまり僕のおじさんがいて、「受かったぞ」と。大学3年の終わり頃でした。
― 俳優デビューとなった「トットチャンネル」の撮影のことは覚えていますか。
髙嶋さん 撮影初日、セリフは一言だけ。みんなが集まるときに誰かがいないという場面で、「かおる君も(いない)」というセリフでした。監督の「じゃあ本番行こう」という一言で空気が変わったんですね。その後、「ヨーイ、ハイ!」と言われて、カチンコ(*情報を記載したボードと拍子木を組み合わせた、撮影用の道具。)の「カチン!」を聞いた瞬間に何かが起こったんです。
― 何が起きたんでしょうか。
髙嶋さん 「これだ、これが俺が求めていた世界だ。」と。オーディションには受かったものの、別にそれほど期待していなかったし、続けるつもりもなかったんですが、「カチン」の音で化学変化が起きました。
― そのときに覚悟ができたんですね。ところで、髙嶋さんは多数の作品に出られていますが、どういう基準で選ぶんでしょうか。
髙嶋さん デビューして10年は、事務所が持ってきてくれた仕事を問答無用でやっていました。今からすればパワハラかもしれませんが、「この脚本家断ったら一生仕事ないぞ。」とか、「この演出家がお前でやりたいと言ってる。君がOKと言わないとこの作品は作らない。」とまで言われたこともあって大変でしたが、今ではこれらの全てに感謝していますね。
― 映画、ドラマ、舞台で、違いはありますか。
髙嶋さん 全部別物ですよ。
― 映画とドラマはカメラの前で演じるので同じかと思っていましたが。
髙嶋さん 映画とドラマも全然違います。ドラマは、テレビ局、ディレクター、プロデューサー、スポンサー、各芸能事務所等の色々な方々の総合作品なんです。でも、映画は、超大作といった例外はあるものの、監督とプロデューサーのものなんです。彼らは作品と心中するつもりでやっています。映画ですと、あるカットを採用するかは、全て監督の一存で決まります。映画は監督のものと言われる所以ですね。あと、舞台と映画は演技の技術が必要ですが、ドラマだと、セリフを間違えたり、緊張していても、熱意で成りきればOKというところがありますね。
― 演技の技術という観点ですが、役者は他の役者の演技をよく見ているものですか。
髙嶋さん 見ますよ。例えば、役者の目とか、表情とか、入り込んでるなとか、滑舌の良し悪しとか、舞台やっているから知らず知らずデカい声になっちゃうんだな、とか。
― 役作りはどのようになさるんですか。
髙嶋さん 例えば、今回の「親愛なる僕へ殺意をこめて」ですと、原作の漫画がありますから、まず漫画を読みました。今回のように漫画が原作の場合は、原作に忠実でないとファンからボロクソに言われると身に沁みているので、その思いで衣裳合わせに行きました。そこで、監督と色々話し合って、スーツのサイズ感や髪型を決めていくわけです。今回の「猿渡」という役は、叩き上げの刑事が実直に頑張ってきたという設定ですから、カッコいいと駄目で、髪型は角刈りが良いんじゃないかと思っていたんですが、同時進行中の別の作品の関係でそれはできませんでした。それで、現場で漫画原作通りのオールバックにしてもらったんですが、その姿を見て、「これだ!」と思いました。
― 外見を決めるのにもそんなに協議を重ねて、そしてキャラクターを固めていくんですね。
髙嶋さん 普段、刑事役をやるときは、巡査から勉強、勉強をやって、巡査長になって、更に推薦されて試験を受けて、認められればやっと刑事になれるという背景を踏まえて演じているんですが、今回はそういう感じではなくて、愚直に、鈍重に生きてきたという面を意識してやっています。
― 原作どおりだとしますと、これから衝撃の展開かと思います。(*取材日現在、第4話まで放送済み。以下、若干のネタバレを含みます。)
髙嶋さん 鈍重に生きてきた男の転落、過ちが始まります。部下の桃井という新人のフレッシュな刑事がまぶしく見えたんですね。でも、この男はサイコパスじゃないんです。今回一番気を付けたのは、サイコパスには見えないようにしよう、サイコパスな目つきだけはしないようにという点です。彼は、もっと色々経験していたら人生が違ったんじゃないかとも思って演じています。とてつもない作品だと思いながらやっていますよ。
― スピンオフを作るなら、猿渡と桃井のストーリーを見てみたいです。ところで、撮影現場を見学させていただいて感じたのは、撮影が長時間に及ぶということです。
髙嶋さん 本作の松山監督とは、ドラマ「鍵のかかった部屋」で初めてご一緒したんですが、よもやこんなに時間をかけて撮る監督とは思っていなかった(笑)。僕の私見ですが、松山監督は色んな角度から何度も撮って、編集でどれを使ったらよいかを決めるというスタイルだったと思うんです。同じシーンを色んなパターンで長回ししたり、寄ったり切り返したり引いたりで色々な絵を撮ったりという、そんな手法を編み出した方というのが僕が諸先輩方から伺った印象です。自分がデビューした頃は、監督の頭の中で固めてきた絵で全て進んでいて、色んなパターンは撮らなかった。もし長々と撮ったら、大御所の役者さんや職人気質のスタッフから「何を撮ってたんだ!」と非難轟々でした。松山監督と初めて一緒に仕事したとき、「なんでこんなに時間かかるんだ」と思っていたけど、でも出来上がった映像を見たときに納得させられましたね。
― そんなに時間をかけて撮るということですと、スケジュール調整も大変そうですね。
髙嶋さん どうしようもない時は、スケジュールの関係で出番を減らすということもあるんじゃないですかね。でも、例えば、行定勲監督(*代表作に、「GO」、「世界の中心で、愛をさけぶ」他多数)は、僕が知っている限りでは、シーン1から順撮りですから、ロケに何度も行ったりする必要がありますので、スケジュールがぴったり合わないとそもそも出演できないですね。
― あと、現場にはとにかくスタッフの数が多いというのも印象に残っています。
髙嶋さん 衣裳、メイク、小道具、照明とか、たくさんの役割が必要ですので、皆、それぞれの立場から細かくチェックしているんですね。でも、監督は全てを見ています。それぞれの立場の方々が色んなプランを持っているけど、監督は、それを的確にまとめなくてはいけない。ある意味では、孤独な立場かもしれません。でも、スタッフの人数については、以前よりだいぶ減りましたよ。コロナ下で最低人数にすることになったんですね。
― コロナが蔓延し始めた当時、裁判はいったん全て中断したんですが、撮影はいかがでしたか。
髙嶋さん 撮影も全部止まりました。最初は、休めると喜んだんですが、でも数日すると、やる気がどんどん失くなってしまって。
― ただ、お家時間が増えたので、エンターテイメント作品を観る時間が増えたように思います。
髙嶋さん 僕も気を取り直して、色んな映像作品を観たり、じっとしていてもしょうがないから、筋トレをしたり、役者の基本である発声をやったりしました。結果的には、今は良い方に向かっていってるんじゃないかなと思っています。
― 最後の質問になりますが、弁護士の印象はいかがでしょうか。
髙嶋さん 弁護士と言えば、やっぱり六法全書覚えて、司法試験受かって、エリート中のエリート、すごいなと思ってます。でも、アメリカのドラマ「ブレイキング・バッド」のスピンオフの「ベター・コール・ソウル」という作品で、裁判官の傾向、法律家の学閥、色んな方の出自等を踏まえた司法取引なんかを見て、弁護士は様々なことをかいくぐって生きている、めちゃくちゃ力強い人たちなんだな、法曹界というのは一筋縄じゃいかない世界なんだなというのを痛感しました。
― 六法全書を全て覚えているわけではありませんが、ただ、法律はあくまでも道具に過ぎなくて、主眼は事件の解決にあるということだと思います。本日はありがとうございました。