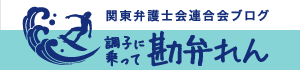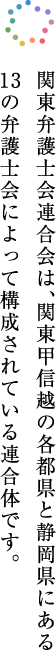
「関弁連がゆく」(「わたしと司法」改め)
従前「わたしと司法」と題しインタビュー記事を掲載しておりましたが,このたび司法の枠にとらわれず,様々な分野で活躍される方の人となり,お考え等を伺うために,会報広報委員会が色々な場所へ出向くという新企画「関弁連がゆく」を始めることとなりました。

重要無形文化財保持者(人間国宝) 有田焼陶芸家
十四代 今泉 今右衛門さん
- とき
- 2024年9月18日
- ところ
- リップル法律事務所
- インタビュアー
- 会報広報委員会委員 森田裕子
今回の「関弁連がゆく」は、佐賀県の有田焼の人間国宝、十四代今泉今右衛門さんです。今右衛門窯の色絵磁器は、江戸期より370年の「色鍋島」の伝統の技と、高い品格を今に伝える「現代の色鍋島」として、国内外で高い評価を受けています。
十四代今泉今右衛門さんは、伝統的な今右衛門窯の作品はもちろんのこと、フランスのバカラ社との共同制作「Bacarat meets IMAEMON」といった、新たな試みにも挑戦するなど、多方面で活躍されています。本年は、2014年に人間国宝に認定されてから10周年にあたり、4月には日本橋高島屋において「人間国宝認定十周年 十四代 今泉今右衛門展」が開催されました。
インタビューでは、青年時代の迷いや葛藤、時を経て心に響いた師匠の言葉、新たな美意識の発見につながる注文主との関係性など、数々の興味深いお話を伺うことができました。
なお、今泉今右衛門さんのWebサイトのURLを掲載いたしますので、記事だけでなく今右衛門さんの素敵な作品もお楽しみください。
今泉今右衛門さん Webサイト https://www.imaemon.co.jp/
― 幼少期はどのような少年だったのでしょうか。
今泉さん 私が育った佐賀県の有田町は、山々に囲まれた場所なので、落ちている木を組み合わせて「基地」を作ったり、家の中でも、段ボールで工作したり。作ることが大好きで、とにかく「いつも何か作っていた。」という記憶です。
― 習い事やスポーツなどはされていましたか。
今泉さん 書道を習っていました。スポーツは、小学生の時は、地域のソフトボールクラブ、中学ではバスケットボール部、高校では卓球部に所属していました。
― 高校生くらいになると、将来どうなりたいかなどを意識してくるかと思いますが、今のお仕事に結びつくような何かきっかけはありましたか。
今泉さん 高校1年生の時に、父(故十三代今泉今右衛門氏)から、どのような進路に進むのか自分で決めなさいと言われました。具体的には、家業の物づくりを手伝いたいのであれば美術大学、家業の商売を手伝いたいなら経済について学べる大学、家業とはまったく異なることをしたければ自分が好きな道でもいいと・・・。私には兄と姉がいるのですが、いつも祖母から「男兄弟が2人いるんだったら、2人して今右衛門の焼き物を作る仕事ができるといいね。」と言われていましたし、物づくりが好きでもありました。そんな経緯もあり、高校1年生の夏に美術大学に進学することを決めました。
― 高校1年生って、結構早い時期に決められたんですね。
今泉さん 美術大学に行こうと思ったら、いわゆる受験勉強だけでなく、デッサンなどの勉強も必要なので早く決めなければいけませんでした。父が東京芸術大学、兄が多摩美術大学だったので、なんとなくムサビ(武蔵野美術大学)しか残ってなかったんですよね(笑)。
― 「残ってなかった。」って。面白い発想ですね(笑)。
今泉さん そうなんですよ。父や兄と一緒のところはイヤだったんですよね(笑)。ムサビに工芸工業デザイン学科というのがあり、これは焼き物に結びつくからいいなと思って、そこに決めました。
― 大学ではどんな勉強をされたのでしょうか。
今泉さん
1、2年生の時は、家電などの工業製品を扱う工業デザイン、建物内部の空間を扱うインテリアデザイン、器などの手作りの物を扱うクラフトデザインという、一通りの形状のデザインを学びました。しかし、その時期は、自分の気持ちを物に託して自分を表現すると言いながら、湧き出る思いがありませんでした。もちろん作ることは好きですけど、こんなデザインを作りたいという思いが無かったんです。気持ちが空回りして、何をすればいいかよく分からないまま課題に挑む日々が続き、大学の成績も下位の状態でした。そんな状況で3年生のときに専門課程を選ぶ時期が来たんですけど、焼き物は将来もできるだろうから焼き物以外にしようと思い、当時、カッコいいなと感じた「金工」を選びました。そうは言っても、相変わらず、授業で出される課題の意味が分からずに空回りばかりしていました。
そんな時、2月に毎日のように雪が降った年があり、友人から雪見酒に行こうと誘われて、一升瓶を片手に玉川上水に向かって歩いていました。そして、街灯に照らされた降り続く雪の下に立った時、中心にすーっと吸い込まれるような感動を覚えたんです。空回りして何も作れなかった時期でしたが、「自分の中に感動する気持ちがあった。」と気付けたことが一番うれしかったですね。感動する想いさえあれば、今は力がなくて物づくりが出来なくても、一歩一歩出来るようになるのでは・・・という、吸い込まれる感動の思いを、その後ずっと持ち続けていました。
ちょうどその頃、父が日本陶芸展で最優秀作品賞である「秩父宮賜杯」を受賞したんですよね。父は日本で一番の賞をとったのに、自分はムサビの80人ほどの学年の下位をウロウロしている。自分はこの先、全く手も届かない仕事を目指しているのではないかと不安を感じていた頃でした。
― 授業の課題で苦心されたとのお話でしたが、課題を通じてどんなことを学ばれたのでしょうか。
今泉さん デザインというのは、形が綺麗だとかそんなことだけではないと。いかに人が使いやすい構造にするか、人を幸せにするか、その事に関する材料・価格・流通など、あらゆる要素を含めてデザインなんだということを学びました。
― 伝統工芸におけるデザインという考え方は、お父様やそれ以前の十二代、十一代と、代々意識されてきたものなのでしょうか。
今泉さん 先代たちは意識してなかったと思います(笑)。その頃のことは分かりませんが、先代たちの物を見ていると、少なくとも昭和30年代ぐらいまでは「この形にこの絵柄をつけて欲しい。」といった、注文主の依頼があったものを作る、というそれだけの考えだったのかと。
― 確かに。もともと、江戸時代も藩主などに「依頼された物」を作っていたわけですよね。
今泉さん 有田の400年は常に依頼された物を作り続けた歴史だと思っています。昔は、一つの仕事として食べていくためだったでしょうし、突拍子もないものを依頼されても、忠実に作ったわけですね。1700年前後にヨーロッパに輸出した物も、依頼主からアルファベットの文字を描くように指示されれば、有田の陶工はアルファベットが何かも知らず、言われるがまま描いていました。
― 大学卒業後は会社員になられたそうですが、どんな仕事だったのですか。
今泉さん 福岡にあったインテリアの会社に就職しました。輸入物の家具や食器など、いい物を扱うので勉強になると父が勧めてくれた会社でした。
― デザイナーとして入社されたのですか。
今泉さん いいえ。一般の社員だったので、最初の1年半程度は店頭に立って、センスのいい家具やカッシーナなどの海外ブランドの家具の販売をしていました。3年間勤務しましたが、接客とバックオフィスという、ビジネスの表と裏を経験できたことは、今の家業にも役に立っていると思います。
― 退職後はどうされたのでしょうか。
今泉さん
父からは、実家にすぐに帰ってもいいし、別の場所で勉強してもいいと言われたのですが、現代彫刻や現代陶芸に興味があり、学生時代に雑誌で鈴木治(すずきおさむ)先生の作品を見てからずっと弟子入りしたいと思っていたこともあり、京都にアトリエがあった鈴木先生にお願いし、1988年に弟子入りさせてもらいました。
ろくろの練習をする際に、先生から「現代のものでも古いものでもいいから、自分の好きな形を選んできなさい。」と言われました。そこで、当時よく通っていた大阪市立東洋陶磁美術館にあった、高麗青磁の瓜型瓶(うりがたへい)という、ちょっと変形した花瓶の形と釉薬(ゆうやく・うわぐすり)の色感が好きで、それをモチーフにろくろの練習をしました。高麗青磁の発色が好きなんですね。釉薬が溜ったところの雰囲気が何とも言えず、その青磁をずっと見ている時、学生時代に雪を見て感じた、すーっと吸い込まれるような感覚と重なったんです。その後、1990年に有田の実家に戻り、家の仕事を手伝ったり、ろくろやデザインの練習を続けました。
― ご実家で練習をする際に、お父様から指導やアドバイスはあったのですか。
今泉さん ほとんどなかったんです。昔の作品を見て研究したり、時間をかけてデザインしてみるなど自分で試行錯誤していました。
― 私たち素人からすると、一人でデザインを決めて、ろくろをまわして、焼いて、絵付けまでされるイメージですが、そうではないんですよね。
今泉さん うちの場合は分業です。デザインまでを自分で決めますが、ろくろや絵付けなど、部分的には職人さんに手伝ってもらってもいます。昭和40年代くらいまでは、個人作家は60%くらいは自分で作らないとダメだ、分業で制作するのはその人の作品とはいえないといったことをよく言われていたんです。しかし分業というのが、単なる大量生産のためになってしまうとよくないけれど、一人で、ろくろも、下絵付けも、上絵付けも、窯の焼成も、デザインもと、全てのスペシャリストになるのは不可能だと思っています。だから、各工程のスペシャリストの仕事を合わせて仕上げていくというのは、一人の人間ではできないことを可能にすることであり、これは案外日本の物づくりの大切な考え方の一つではないかと私は思っています。
― 有田焼の他の窯元も分業制なんですか。
今泉さん もちろん、日本の作家で、一人で全ての作業をする方もいらっしゃいますが、磁器の場合は分業制が多いです。分業制で制作しても全ての制作のコンセプトは自分で決めるので「十四代の今右衛門の作風」になるんですよね。

色絵薄墨墨はじき四季花文蓋付瓶
― 確か、お父様が突然逝去されて、大変だった時期がありましたよね。
今泉さん 父が70歳くらいのときに、私が父の後を継ぐということは覚悟しました。その頃は父も元気で、かかりつけの医師からも「90歳まで大丈夫ですよ。」と言われていたのですが、2001年に75歳で他界しました。私が38歳の時でした。父が亡くなった悲しさはもちろんありましたが、それよりも職人さんへの給料をはじめとする家業の経営が一番の心配事でしたね。
― お父様が亡くなられた翌年に十四代を襲名され、その後のご活躍については、多方面で取り上げられてますよね。ですから今回は、これからの創作活動や夢などについてお聞かせいただければと思います。
今泉さん お正月の窯出しの時に、マスメディアの取材で「今年はどんな物を作りたいですか?」とよく聞かれます。しかし、どんな物を作ろうかというよりも、依頼されたことに向かって真摯に作っていくという意識なんです。そのように作っていくと、自分が思いもしなかった雰囲気や色調が出てきて、新しい美意識が見つかるんです。だから作りながら、私としては、どんな美意識が見つかるかを楽しみにしているんです。
― お客様が可能性を引き出してくれるって感じでしょうか。
今泉さん
そうなんです。自分の意識で「こんなものを作ろう。」と進めると、理屈張ってしまうんです。でも、お客様からは突拍子もない依頼もありますから。そうやって依頼を受けて物を作ってみると、自分では想像もしなかった物が出来上がるんですよね。それはすごく大切なことかと思っています。
師匠の鈴木治先生のもとでの修行時代に、先生が私に「今泉君、我々が作っているのは陶芸なんやで。」とおっしゃたんです。当時は意味が分からなかったのですが、先生が亡くなられた後、ある展覧会で先生が話されていた文章を目にしました。そこに記されていたのは、「陶芸は焼くと収縮するし、中に空気が入っていると破裂する。そうすると、口をどう作っていこうかとか、収縮を想定してどうしようかとか、火で焼くという自然の作用を受け入れなきゃいけない。だから自分で一から最後までできる芸術の仕事と陶芸は基本的に違う。受け入れることが大切な仕事なんだ。」といったことでした。
薪をくべる窯で焼くと、焼き物の表面のガラス質がすごく柔らかく仕上がるんですよね。若い頃はこの窯の火が作るというのが大嫌いだったんです。そんなのは、その人の作品じゃなくて窯が作った作品だろうと思っていたんですよ。実際、有田に帰ってきて現代彫刻のような物を作っているときも、窯から上がってきたものを削ったりして自分の意識の中に押しつけて作っていたんですが、40代半ばになって、鈴木先生の言葉に出会い、その頃に、薪をくべる窯から出てくる釉薬の肌合いの雰囲気がすごくいいので、それを排除するのではなく、受け入れることが大切なんじゃないかなと思い始めました。
それと工芸って、昔から注文主の依頼によって作られるというのが大きな特徴ですが、その最高の状態が千利休と長次郎の関係だろうと言われています。長次郎の黒の茶碗というのがあるのですが、あれは、利休が「こういった物を作れ。」と注文すると、長次郎がそれ以上のものを作って、さらに利休がそれ以上の美意識のものを依頼するという、そういった関わりの中で、あの名品が生まれたのだと思います。だから今は、自分を中心として物を作るんじゃなくて、受け入れて作ることの大切さがあるのではないかと思っています。

色絵薄墨墨はじき雪文鉢
― 素人からすると、伝統工芸の陶磁器と聞くと、展覧会や美術館に飾ってあるものといった感覚になってしまうのですが。
今泉さん 使ったり飾ったりして、暮らしの中に存在して欲しいなといつも思ってます。触ったときの指当たりとか滑りにくさとか、そういったことを含めてのデザインであるし、価格は高いかもしれませんが、そういう物を使う時ってほどよい緊張感を感じると思うんです。ほどよい緊張感の中で使うと、味ってよくなるんですよね。緊張しすぎると逆に味が分からなくなってしまいますが(笑)。有田では、毎年ゴールデンウィークの時期に陶器市が開催されます。そういう機会なども利用して、今右衛門の作品でなくてもいいんですけど、是非ご自分の好きな物を探しにきてみてください。