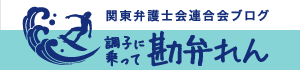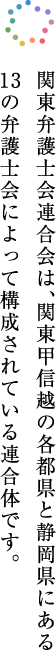
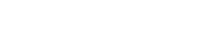 関弁連とは?
関弁連とは?
関弁連って何の略ですか?
関弁連というのは、関東弁護士「会」連合会のことで、東京高等裁判所管内の13の弁護士会によって構成されています。東京の三弁護士会(東京、第一東京、第二東京)と、関東地方の弁護士会(神奈川県、埼玉、千葉県、茨城県、栃木県、群馬)のほか、甲信越の弁護士会(山梨県、長野県、新潟県)及び静岡県の弁護士会が連合した組織です。
関弁連に所属する弁護士の数は約2万9千人で、日本の弁護士の約62%が関弁連に属しています。
全国には、「弁護士会連合会」(弁連)が、関弁連の他に、全国の高等裁判所に対応して、北から北海道、東北、中部、近畿、中国、四国、九州に設けられています。
また、全国組織である「日本弁護士連合会」(日弁連)は、全国52の弁護士会及びそこに所属する弁護士・弁護士法人を構成員(会員)としています。つまり、52弁護士会は、日弁連の会員であると同時に、各地の弁連の構成員でもあるわけです。
日弁連は、国家機関から監督を受けない「弁護士自治」を有し、この自治権の下に、弁護士会及び弁護士等の指導及び監督を行い、また、全国レベルで憲法、人権、災害支援、刑事司法と民事司法の改革、法曹養成、裁判員制度、男女共同参画等といった重要な諸課題について市民の視点から取り組んでいます。
関弁連を始めとする各地の弁連は、各地で日弁連のこういった活動のサポートを務める一方、地域における諸課題に取り組むと共に、構成する弁護士会の連携・交流を図るための諸活動を展開しています。
どんなことをしているのですか?
定期弁護士大会やシンポジウムなど、13弁護士会が協働で行っている事業が沢山あります。最近では、東日本大震災の被災者支援活動もそうです。福島から関弁連管内に避難しておられる方は沢山おられます。お互いに情報交換したり研修をしたりしながら、被災地にアクセスしやすい会は、現地に行って法律相談をすることに力を入れ、遠い会は地元で避難して来られた方々を支援したりして、協働して被災者支援に取り組んでいます。
関弁連の課題はどんなこと?
関弁連は、日本最大の弁護士会連合会ですが、所属弁護士の4分の3は東京の三つの弁護士会に属し、残りの4分の1の弁護士がそれ以外の弁護士会に属しています。その環境の違いから、巨大都市東京の弁護士会と10県に属する弁護士会の間では、かなり意識が違っています。この違う弁護士会同士で、情報を共有し協働していく工夫が求められています。
理事長就任にあたって

2025年度理事長
種田 誠
ご挨拶
2025年度理事長に就任いたしました種田誠(茨城県弁護士会所属、28期)です。第一東京弁護士会の渡部朋広副理事長はじめ、常務理事、理事及び監事の皆様と共に、1年間関弁連の運営に務めてまいりますので、よろしくお願いします。
茨城県弁護士会からは、1980年度に故関谷信夫弁護士が関弁連理事長を務めて以来、45年ぶりとなります。私自身は、2001年度茨城県弁護士会会長、2003年度に日弁連副会長を本林徹会長のもとで務め、司法改革に携わってまいりました。2006年4月から3年間日本司法支援センター茨城地方事務所長を務め、また、2008年4月から弁政連本部副理事長の任にありました。私が弁護士会会務を実質的に行っていたのは20年も前のことですので、渡部副理事長には、大きな負担をかけることになること必至で申し訳なく思っています。
関弁連を組織する東京高裁管内13弁護士会の所属弁護士数は2万9300名を超え、日弁連加入弁護士約4万7000名の6割を上回る弁護士で構成されています。関弁連からの提言やその活動は、日弁連の活動にも大きく反映するばかりでなく、日本の司法のあり方や運営に多大な影響を与えております。
一方で、数千人を超える弁護士が所属する東京三会と、125名余の少数会員で構成された会を含む十県会とでは、各々の弁護士会が抱える諸施策・諸問題も異なるものとなります。協力・協調体制のあり方も困難を極めることがあります。とはいえ、再審法改正・選択的夫婦別姓制度の実現など司法が解決しなければならない諸課題を成し遂げて行くには、すべての弁護士会の一層の連携・強化が不可欠です。
地方単位弁護士会である十県会選出の理事長として、家庭裁判所の充実など地域司法の強化のために、管内弁護士会の協力を得て、弁護士数の多さという関弁連の強みを生かし、諸課題の実現に努めていきたいと考えております。
2025年度関弁連の重点課題や施策の充実に努めるべく、副理事長・常務理事・理事・監事の皆様や事務局職員と全力を尽くしてまいります。