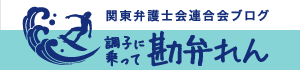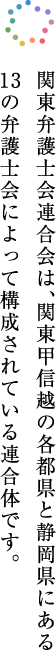
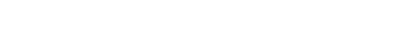 宣言・決議・意見書・声明等
宣言・決議・意見書・声明等
2025年度(令和7年度) 意見書
機能性表示食品に関する意見書
2025年(令和7年)7月22日
関東弁護士会連合会
機能性表示食品は、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性を表示できるものであるが、当連合会は、2019年3月19日付「機能性表示食品制度に対する意見書」において、機能性表示食品制度は、安全性に疑義があることや機能性の科学的根拠が不十分であることから、廃止すべきであるとの意見を述べた。
しかしながら、機能性表示食品と同じく保健の機能性を表示することができる特定保健用食品については、1000件程度にとどまっている一方、機能性表示食品については、2015年以来増加し続け、わずか10年で7000件以上の届出がなされている。
その後、2024年8月23日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第71号)が公布され、安全性や機能性、製造管理についての遵守事項が加えられたが、以下のとおり、なお問題点があるため、改めて意見を述べるものである。
第1 意見の趣旨
- 1 機能性表示食品制度については、廃止すべきである。
- 2 仮に機能性表示食品の制度を廃止できない場合であっても、食品の安全性を確保し、機能性の科学的根拠が十分合理的と評価できるものに限定するように必要な措置を講じるほか、機能性表示食品の表示についても、適格消費者団体の差止請求権の対象とすべきである。
第2 意見の理由
- 1 機能性表示食品に関連する問題点
-
⑴ 機能性についての科学的根拠が乏しいことを理由とする措置命令等
機能性表示食品については、2023年6月30日に「血圧を下げる機能性取得」「中性脂肪を低下させる機能性取得」などの効果を謳った機能性について合理的な根拠がないことを理由に優良誤認に当たるとしてさくらフォレスト株式会社に対し、不当景品類及び不当表示防止法に基づく優良誤認により措置命令が出された[1]。また、当該措置命令の対象となった商品の届出内容と同一の科学的根拠である商品等88件に対し、科学的根拠として疑義がある点が指摘され、いずれの事業者からも科学的根拠がある旨の届出がされることはなく、撤回申出がなされた[2]。
同様に、2023年12月5日には、痩身効果、顔面の美白効果等を謳ったと評価できる表示について科学的根拠がない等として株式会社アリュールに対し、不当景品類及び不当表示防止法に基づく優良誤認により措置命令が出された[3]。
これらの措置命令の対象となった商品については、さくらフォレスト株式会社が、販売期間が短い商品でも1年半もの間販売を行い、2商品で合計36億円超の売上を計上していたほか[4]、株式会社アリュールについても、広告が確認できた範囲だけでも8か月前から販売を行っていた。
すなわち、現行法では、機能性について科学的根拠が脆弱で、事業者自身が指摘を受けて撤回するような食品であっても、一定期間消費者に対し、機能性を謳い販売することで多額の収益を得ることができる環境にある。また、同一の科学的根拠に依拠した措置命令を受けていない機能性表示食品88件の全てについて、撤回の申出がなされている点に鑑みれば、機能性に科学的根拠が乏しい食品の存在は、ほかにも存在すると疑わざるを得ず、適切な市場環境が阻害されていると言わざるを得ないという問題があげられる。 -
⑵ 買上調査における製品自体に不備が散見されていること
消費者庁は毎年食品の買上調査を実施しているところ、特別用途食品及び特定保健用食品については、2020年から2023年まで、全て関与成分等は申請等資料のとおり含有されていたと報告されている。
一方、機能性表示食品については、2020年度で80品目中1件、2021年度で81品目中1件、2022年度で103件中2件、2023年度で84件中2件について、関与成分等が申請等資料の記載どおりに含有されていないことが判明している。当該届出の申請等資料の記載どおりに含有されていない製品が毎年存在しているにもかかわらず、具体的商品名や機能性関与成分名は明らかにされないため、消費者において当該問題点を把握することすらできない。当該買上調査の結果に照らしても、製造過程について不備が疑われる商品が一定数存在するという問題があげられる。 -
⑶ 小林製薬株式会社による紅麹関連食品の健康被害
2024年3月、小林製薬株式会社が機能性表示食品として製造・販売する「紅麹コレステヘルプ」その他紅麹原料を含む計3製品を摂取したことにより、多数の重篤な健康被害の発生が報告された。同被害者数は、2025年3月16日時点において、延べ2710名が医療機関を受診し、死者数が408名、入院治療を要した者は558名と重篤な健康被害が報告されている。
当該健康被害は、その後の調査により、製造過程における青カビの混入が原因であるとされ、機能性表示食品固有の問題ではないと考えられる。
しかしながら、機能性表示食品の安全性についての科学的根拠も事業者に委ねられている以上、安全性のテストが乏しいために機能性表示食品そのものを原因とした健康被害が将来生じる可能性は否定できないのであり、機能性を謳うことで、消費者が過剰かつ長期間摂取することが想定される一方で、安全性についての担保が不十分という潜在的な問題は今なお存在している。 -
⑷ 消費者の認知度が依然低いままであること
「令和5年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」[5]によれば、機能性表示食品について、「どのようなものか知っている」は17.5%にとどまり、「聞いたことはあるが、どのようなものか知らない」は65.9%、「聞いたこともなく、どのようなものかも知らない」が16.6%とされている(Q40_3)。
また、機能性表示食品の説明について正しいと思うものを回答させる4択での質問に対しても、「分からない」と回答されたものを除くと「表示されている効果や安全性について国が審査を行っている」という誤回答が最も多く19.9%に上り、「事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示したものである」と正しい回答をした者は、16.8%にとどまっている(Q51)。
当該アンケート結果からも、依然として消費者において、機能性表示食品の機能性・安全性について、国が認めていると誤認している者が多い。
さらに、機能性表示食品の届出情報について、消費者庁ウェブサイトで確認できることを知っている割合はわずか12.9%に過ぎず(Q52)、届出された科学的根拠を確認して消費者が摂取を検討するという状況には程遠く、事業者が表示した機能をそのまま信用しているのが実態である。
-
⑴ 機能性についての科学的根拠が乏しいことを理由とする措置命令等
- 2 食品表示基準等の改正によっても、問題点が解消されていないこと
-
⑴ 2024年8月23日、食品表示基準等については、概要以下の改正がなされた。
- ① 届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供すること。
- ② 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないこと。
- ③ 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品についてはGMP(Good Manufacturing Practice)に基づく製造管理を行うこと。
- ④ 「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置などの方式等を見直すこと。
- ⑤ 届出者の遵守事項として、届出者は、遵守事項を遵守していることを届出後一年ごとに自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告すること。
- ⑥ ア)当該食品に関する表示の内容、イ)食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、ウ)安全性及び機能性の根拠に関する情報、エ)生産・製造及び品質の管理に関する情報、オ)健康被害の情報収集体制及び カ)その他必要な事項について、届け出られるべき情報として具体的に規定するほか、様式等については内閣府告示で定めること。
- ⑦ 届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合には、販売前の届出資料の提出期限について、原則60営業日を特例として120営業日とすること。
- ⑵ これらの改正は、紅麹を含有する関連食品の健康被害を契機にしているものであるが、科学的知見について事実上の審査が加えられたほか、いわゆるサプリメント類についての製造工程の厳格化がされたことなど、安全性、機能性について、一定の制限を加えた点は評価できる。
-
⑶ しかしながら、依然届出制が維持されたため、許可制と異なり、機能性についての科学的根拠が不十分な食品であったとしても、食品関連事業者等が届出を撤回しなければ、届出自体は残ることになる。また、事後的に安全性に問題があること等が明らかになった場合でも、行政庁の判断による取消の概念はなく、同様の問題が生じる。
さらに、食品関連事業者の製造工程について、どの程度監督がなされるのかが不明である上、仮に遵守事項への違反があった場合でも、単に機能性表示(ヘルスクレーム)ができなくなるというだけで、違反事業者に対して当該機能性食品の販売停止を命じたり、課徴金等の経済的不利益処分を課したりする効果まではなく、結果として、遵守事項が守られていない食品が流通しつづける恐れがある。
現に機能性について科学的根拠が不十分な食品が多数存在していたにもかかわらず、販売が継続され事業者が多額の売上を計上していたこと、申請等資料の記載どおりに含有されていない製品が存在していたこと、機能性を重視した消費者が過量に長期間摂取する可能性があるにもかかわらず、安全性の科学的根拠が不十分であること、消費者において、機能性表示食品の認知度が低いままであり、事業者の表示する機能性をそのまま信用して製品選択がなされているという実情に鑑みれば、機能性表示食品の制度については、食品の販売の適正性や国民の健康の保護を図っているとは言い難い。
したがって、意見の趣旨第1項記載のとおり機能性表示食品の制度については、廃止するべきである。
機能性表示食品の制度を廃止したとしても、特定保健用食品として、安全性・機能性について厳格な審査を受けて、販売する道は残されている。機能性を謳う以上、消費者が口にする食品についての機能性ないし安全性に関する科学的根拠については、厳格に審査されるべきであり、当該基準を緩めることは妥当でない。
-
⑴ 2024年8月23日、食品表示基準等については、概要以下の改正がなされた。
- 3 機能性表示食品を廃止しない場合の措置等
- ⑴ 仮に、機能性表示食品の制度を廃止することができない場合であっても、食品の安全性を確保することや機能性の科学的根拠を十分合理的と評価できるものに限定することが不可欠であり、改正された食品表示基準等では不十分である。
-
⑵ 例えば、機能性表示食品についても、届出制を改め許可制とすることが考えられる。許可制とすることで、入り口段階から、安全性が不明な食品や機能性の科学的根拠が十分でない食品を排除することできる。また、許可後であっても、事後的に科学的根拠が十分でないとなった場合や製造工程の問題等が生じた場合には、許可を取り消すなどして、行政側で一定の規制を果たすことができる。消費者庁の担当者の説明においても、機能性表示食品制度の届出は、本来禁止の解除であり、許可制にすべきところを、簡易な手続で機能性表示(ヘルスクレーム)ができる制度としたもので、限りなく許可に準じた形でたまたま届出という制度を用いたものとの説明がなされている[6]。したがって、仮に機能性表示食品制度を廃止できない場合であっても、許可制に変更することは必要である。
そのほか、既存の機能性表示食品についても、科学的根拠の乏しい食品がないか積極的に調査して、問題がある場合には不当景品類及び不当表示防止法の優良誤認として措置命令を発出することや、事業者のGMP等の製造工程等の監督を強化し、遵守事項が守られていないときは、指導・措置命令・公表を積極的に対応すべきである。
加えて、多くの消費者が、機能性に着目しているに過ぎず、食品の安全性や、機能性が事業者の自主的な責任に委ねられているとの認識が少なく、その根拠のウェブサイトを見ることもなく、消費行動に移している実態は改善することが望ましい。そこで、消費者庁において、消費者に対し、制度の内容が浸透するよう、定期的な広報をすることが強く求められる。 - ⑶ 更に、食品表示法第11条では、食品表示基準に違反した一定の表示について差止請求権の行使の対象としているが、機能性表示食品については、適用がない。しかし、機能性表示食品についても、遵守事項等が守られず食品表示基準に合致しない食品については、その表示を差し止めるなどの機動的な対策が求められることに変わりはない。そこで、機能性表示食品の食品表示基準に違反する食品については、適格消費者団体の差止請求権の対象とするべきである。
- ⑷ 以上のとおり、仮に機能性表示食品の制度を廃止できない場合であっても、食品の安全性の確保や機能について科学的根拠について十分合理的と評価できるものに限定するべく、許可制への変更や監督強化、措置命令等の積極的な運用、消費者への広報の強化、適格消費者団体の差止請求権の対象とする等のその他の必要な措置を講じるべきである。
[1] 消費者庁 令和5年6月30日「さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
[2] 消費者庁 令和5年8月17日 「機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について(情報提供)※随時更新」
[3] 消費者庁 令和5年12月5日「株式会社アリュールに対する景品表示法に基づく措置命令について」。なお、科学的根拠のほか、「消費者庁が認めた」「国が認めた」と表示していたことも優良誤認の理由とされている。
[4] 消費者庁 令和7年3月19日「さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」