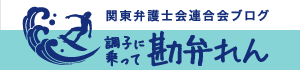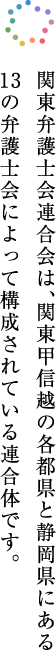
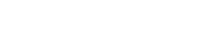 シンポジウム
シンポジウム
2024年度 初等・中等教育における弁護士の役割
2024度シンポジウム委員会委員長 根本 信義(茨城県)
1 本シンポジウムの狙い

9月27日(金)午前10時から、水戸市民会館において、会場参加とWeb配信のハイブリット方式による本シンポジウムを開催した。会場参加が326名、Web参加が89名であった。
関弁連のシンポジウムとしては、これまでにも2002年に「子どものための法教育」、2011年には「これからの法教育」と、2度にわたり法教育関連のテーマを扱っている。いずれもその年の大会宣言において、子どもに対する法教育の必要性と重要性を訴え、教育機関と連携しつつ、法教育を普及させることを宣言した。
そうして、全国の各弁護士会において「法教育」に関する委員会が作られ、各弁護士会に小中高の児童・生徒を呼んで「法教育」授業を行うイベントを開催したり、実際に学校へ出前授業に行くなどの活動を行うようになった。
しかしながら、弁護士会としては、教育機関や県・市町村との連携も十分に取れず、「法教育」がどうあるべきかという核の部分を十分に煮詰めることができないまま、場当たり的に対応せざるをえないというのが実情であった。
さらに、その後の社会情勢の変化から、弁護士に対して、特定の分野に特化した教育が要請され、様々な委員会が学校に出向くなどして教育活動を実施するようになってきた。例えば、18歳選挙権のための主権者教育を憲法委員会が、18歳成年のための消費者教育・労働教育を消費者委員会や労働対策委員会が、いじめの多発によるいじめ予防授業を子どもの権利委員会が担当するといった具合である。
こうした諸委員会の活動に対して、そこに通底するものは、弁護士と連携する授業を通じて子どもたちに「個人の尊重」という理念・価値を身に着けてもらうことではないのか、また、弁護士会としてもっと効率的に学校と協働して行うことはできないか、という強い思いがあった。そうしたところ、2020年度から始まった学習指導要領は、「社会に開かれた教育課程」を掲げ、教育課程の実施に当たって、地域の人的資源等を活用し、学校教育を学校内に閉じずに社会と連携しながら実現することとされた。そこで改めて、学校から弁護士に対してどのような授業が望まれているのか、また弁護士会として効率的に対応するにはどうしたらいいのか、を考えるために、「初等・中等教育における弁護士の役割」をテーマとすることにした。
2 シンポジウムの内容
(1) アンケートの実施報告
委員会としてまず行ったのが、関弁連管内の各都県の小・中・高に実際に弁護士に対してどのような需要があるのかのアンケートと、各弁護士会でどの委員会がどのような教育活動を行っているかのアンケートをとることだった。シンポジウムでは、まずこのアンケートの分析結果について、関山英忠副委員長から報告してもらった。学校アンケートについては、関弁連管内の小・中・高のうち2625校から回答があり、弁護士と連携して授業を実施したことがあると回答した学校が16%だったのに対して、弁護士と連携して授業を行いたいと答えた学校は81%に上り、学校側からは、連携できる授業を紹介して欲しい、費用を開示して欲しいなどの要望があることが紹介された。
(2) 授業案の紹介
報告書では、学校からのアンケートで弁護士と連携を希望すると答えてもらった15個の項目について、1つ以上の授業案を作成したので、シンポジウムではこれを次の4つのカテゴリーに分けて報告した。
① 法教育カテゴリー
② 契約・消費者教育カテゴリー
③ 労働・家族教育カテゴリー
④ いじめ・非行予防、差別をなくす教育カテゴリー
作成した授業案について1つ1つ説明する班、特に学校に出前授業に行った授業案について丁寧に説明する班、寸劇を織り交ぜて視覚的に訴える班など、それぞれ工夫を凝らした発表がなされた。
(3) パネルディスカッション
パネリストには、国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官の磯山恭子氏、茨城県教育庁学校教育部高校教育課指導主事の飯濵毅氏、同義務教育課指導主事の篠﨑智典氏、それに根木孝久シンポジウム委員に入ってもらい、コーディネーターは私が務めた。
まず、教育関係者の方々から「社会に開かれた教育課程」としてどのような実践があるかをお聞きし、根木委員からは浜松市との法教育推進に関する協定の話をしてもらった。その上で、学校に弁護士を呼ぶ必要性、費用の問題など、今後の弁護士会と学校との協働がどうあるべきかについて討論をした。
3 弁護士が学校において教育活動に取り組むための体制作りに関する宣言
本シンポジウムを踏まえて、関弁連定期大会において、①弁護士会の各委員会の授業内容の再点検と委員会相互協力体制の整備、②弁護士の授業能力の向上のための体制作り、③授業内容の共有・公開、④学校側との協同体制の確立を内容とする標記の宣言を提案し、全会一致により採択していただいた。
これを契機として、学校教育において子どもたちに自由で公正な民主主義社会を支えているものが「個人の尊重」という理念・価値であることを理解してもらうことが何よりも重要であり、そうした教育に携わることもまた弁護士にとって1つの重要な使命であることを一人でも多くの弁護士に理解していただけることを願ってやまない。
シンポジウムに際し担当のシンポジウム委員会が作成した報告書を公開しますので、ご参照ください。
※紙媒体の報告書もお譲りすることができますので(先着順)、ご希望の方は関弁連事務局(03-3581-3838)までご連絡ください。