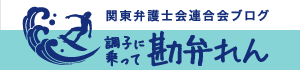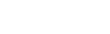 法教育
法教育
多様な性と学校生活・日常生活
最近の調査によれば、日本における性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)の割合は、8~10%であるとされる。これは、血液型がAB型の人の割合、左利きの人の割合とほぼ同じである。もっとも、「性的少数者」といっても、その内容は一様ではない。
性の多様性を考える際には、①生物学上の性(外性器・内性器に基づく区別)、②性自認(自らの主観的認識に基づく区別)、③性的指向(恋愛対象・性愛対象に基づく区別)、④性表現(服装、仕草、言葉づかい等に基づく区別)といった視点から多角的に考察することが大切である。また、①~④の中にも、「様々な違い」(多様性)があることに注意する必要がある。
性的少数者の権利を巡っては、近時、最高裁は、従来の判例を変更し、性同一性障害特例法に基づく性別変更のための要件の一部が違憲(無効)であるとの判断を示した。同じく最高裁は、中央官庁におけるトイレの使用制限(戸籍上の性は男性であるが、社会的には女性として生活している者が、自身の執務室と同階の女性用トイレの使用を禁止されていた事案)について、そのような制限は、著しく妥当性を欠いており、裁量権の逸脱・濫用があるとの判断を示した。
また、現在、各地で同性婚を求める訴訟が提起され、地裁・高裁では、同性婚を認めない現在の婚姻制度は憲法に反するとの判断が相次いでいる。
しかし、一方では、性的少数者の権利を保護することにより、他者の権利・利益や従来の社会・倫理規範との衝突が起きる場面も想定される。
本勉強会では、以上のような性的少数者の実態や裁判例を取り上げるとともに、学校における授業の実情についても意見交換をした。
勉強会に出席した教員からは、性的少数者を巡る問題については、生徒の中にも当事者がいる可能性があり、(当該生徒への配慮を考えると)具体的な議論をすることは難しく、表面的な知識を教える程度に留まっているといった意見や、実際に性的少数者に関する授業をした後には保健室に相談に来る生徒がいるといった意見があった。
また、出席した弁護士からは、地方自治体における啓発活動や教育上の取組みを紹介した上で、生徒の発達段階に応じた継続的な教育が必要であるといった意見が出た。
以上