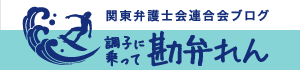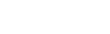 法教育
法教育
選挙と表現の自由
日本では、18歳未満の者による選挙運動は禁止されている。その趣旨は、判断能力の未熟な者を保護するためであるとされる。他方、平成28年6月には選挙権年齢が18歳に引き下げられ(その当時は、成年年齢は20歳のまま)、令和4年4月からは成年年齢自体が18歳に引き下げられた。
18歳未満の者による選挙運動の禁止を巡っては、令和7年2月28日、16歳~18歳の高校生4名が選挙運動ができる地位にあることの確認等を求める訴訟を提起したとの報道があった。
これ以外にも、日本の公職選挙法は、選挙運動に関して広範な規制を設けている(違反に対しては罰則も科される。)。
選挙が民主主義を支える根幹であることからすれば、一方では、国民一人ひとりによる自由な言論が保障される必要があり、他方では、公正な選挙を実現するためには一定の制約を設けざるを得ない。
そのため、表現の自由の保障と制約の均衡点をどのように理解すべきかが重要な問題となる。
以上のような問題意識に基づき、本勉強会では、選挙運動に関する規制の在り方と表現の自由の関係を取り上げることとした。併せて、中学校・高校における選挙に関する授業の概要について意見交換をした。
選挙運動に関する規制については、古くから事前運動の禁止、個別訪問の禁止、文書図画の頒布・掲示に関する規制を巡って判例が積み重ねられてきた。
判例の趣旨は、要するに、選挙運動に関する規制の目的は、表現行為を無制限に認めた場合に生じる種々の弊害を防止することにあり、その手段は、表現内容そのものに対する制約ではなく表現の手段・方法に対する制約(間接的・付随的制約)であるから、これらの規制は憲法には反しないというものである。
出席した弁護士からは、表現の自由に対する制約を検討する際には、規制の目的が何であるか、規制手段がどのようなものであるか、目的と手段との間の関連性を具体的に検討する必要があるという説明があった。
また、出席した教員からは、生徒たちは、選挙が民主主義にとって極めて重要であるということを知識としては理解しているものの、自分事として実感していない印象があるという意見が出た。その上で、授業で模擬投票をおこなったり、生徒会の選挙をおこなったりすると、意識が変わる生徒もいるという話があった。
以上