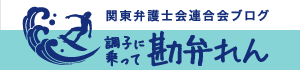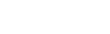 法教育
法教育
「正義」について
「正義」の概念は多様であるが、①どのような内容を「正義」であると主張するのかという正義論の「内容」に関する側面と、②何に関する正・不正を論じるのかという正義論の「対象」に関する側面から考察することが可能である。
歴史的には、正義論は、人の性格を対象とし、それが良い状態であることが正義であるとする徳倫理学的な考え方から始まり、人の行動基準を対象とする功利主義と義務論の対立を経て、「何が公平・公正な社会なのか」という社会構造の在り方に関する契約主義的な考え方へと発展してきた。
このような正義論の歴史的展開の背景には、それぞれの時代における社会情勢等が大きく関わっている。その意味において、「正義」について考えることは、現代社会における諸課題を解決する視座を得るだけでなく、当時の時代背景を知る契機ともなる。
他方、法教育の観点からは、「正義」の概念は、①配分的正義、②匡正的正義、③手続的正義の3つに分けることができる。
配分的正義とは、利益や負担を分配する際に求められる正しさや公平さである。その際に考慮すべき要素としては、「必要性」、「能力(適性)」、「ふさわしさ(適格性)」が挙げられる。
匡正的正義とは、不正な行為や生じた損害に対して正しく対処することをいう。犯罪に対する刑罰や損害賠償がこれに当たる。
手続的正義とは、結果や内容の決定・是正に至るまでのプロセス自体の正しさを求めるものである。
勉強会に出席した教員からは、実際の授業では、初めから「功利主義」や「義務論」といった考え方を教えるのではなく、あるテーマを題材に生徒に議論をさせ、出てきた意見に対して「それは~という考え方に近いね。」といった解説をつける形で理解を促しているというコメントがあった。
また、歴史(世界史)に詳しい教員からは、現代の西洋哲学は、古代ギリシアで誕生した正義論が、いったんアラブ地域を経由し(その間、ヨーロッパでは、キリスト教の影響により古代ギリシア流の哲学は衰退していた。)、その後、再びヨーロッパに“逆輸入”されたものであるという説明があった。
以上