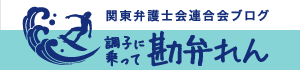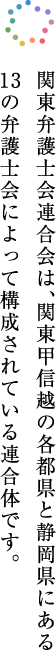
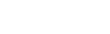 法教育
法教育
『中高生のための法と学校と社会』
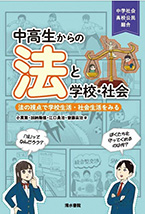
2023/09/15 小貫 篤 /加納隆徳 /江口勇治 /齋藤宙治 編著
発行:清水書院 A5判 120頁
【内容】
社会問題を考える…といっても、社会に出ていない生徒たちにとっては「どこか遠いところで起きている問題」に感じられるだろう。本書は、生徒たちにも考えやすいような身近な問題に対して法的な解説をしたものである。
本書の事例は、高校教員であった著者(小貫篤氏、加納隆徳氏。現在は大学教員。)が、担任や部活の指導・生活指導・学校内トラブルに対応してきた実際の経験をもとにして作成された。
そして本書の「法的な解説」は、「法の●●条により違法」というような「答え」を教えるものではない。法の価値観や、そのような価値観が生まれた背景などにふれながら、どんな思考過程を経ればその問題が解決できるのかを示すものである。
このプロセスを学ぶことで、執筆協力者である江口勇治氏の言葉を借りれば、トラブルに対する「対応を選択・判断し、分析・総合の結果や決定をわかりやすく伝える『知的で倫理的な道具』」を学び、「自分やみんなの利益になり被害を縮小」できるようになることを目指すのである。
これは、学校内のトラブル解決に役立つだけでなく、社会に出てからも役に立つ。
本書にはイラストや図解が豊富に使用されている。中高生の方には、ぜひ本書を手に取って、法を用いた「知的で倫理な」思考方法を学んでほしい。
【主要目次(内容と構成)】
はじめに
Chapter1 家庭と法
1 トラブルをどう解決する? ―交渉から訴訟まで話し合いの方法―
2 契約で社会がまわっている? ― 『リトル・マーメイド』で考えるー
3 ケーキや地位をどう分ける? ―公平な配分か平等な配分かー
4 事故を起こしちゃったらどうすればいい? ―過失に対する責任の取り方―
5 だれと結婚する? ―SOGI と同性婚をめぐってー
6 親は亡くなった子どもの SNS を見れる? ―プライバシーと相続―
Chapter1へのコメント 法学のイメージ
Chapter2 学校と法
1 宗教を理由に授業をうけないことは認められるの? ―日本人の宗教観―
2 子どもをデザインしていいの? ―生命倫理を考える視点―
3 オンライン文化祭で音楽は使えるの? ―著作権とその利用ー
4 生徒会長はどうきめるのか? ―えらび方を考える―
5 高校生は選挙運動を手伝える? ―政治参加の方法ー
6 子どもと大人の境目はどこ? ―責任を負う年齢とは―
7 ブラックバイトって何だ? ―労働と契約を考える視点―
Chapter2へのコメント 法学の立場から法を学ぶとは
教育学の視点から みんなの「公共」の学習の基本を考える
おわりに
以 上