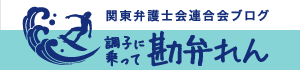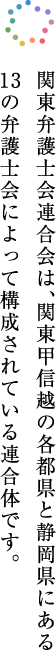
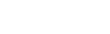 法教育
法教育
『“法”を教える-身近な題材で基礎基本を授業する』
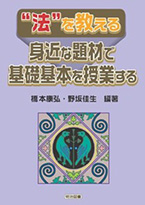
2006/7/24 橋本 康弘 ・ 野坂 佳生 編著
発行:明治図書出版 A5版 164頁
【内容】
従来、“法”の学習というものが、主として憲法(政治制度・司法制度)を学ぶというもので、“法”の授業のねらいが憲法の条文や判例・機構の制度理解にとどまっていた。
本書は、そこから脱却し、「社会力・社会性の育成の必要性」という課題に応えることを意図した新しい“法”の授業を提言するものである。
この提言をめざし、本書では、第Ⅰ章では「理論編」として新たな“法”の学習のあり方について論究する。
次いで、第Ⅱ章及び第Ⅲ章では、第Ⅰ章の「理論編」を踏まえた「実践編」として、以下の(1)~(5)のテーマに関する指導案が紹介されている。
(1)「“法”関係のニュースを扱う」
(2)「“法”を理解し“法”を反省する」
(3)「“法”を理解するとともに“法”を批判する」
(4)「紛争を解決する」
(5)「社会に参加し提案する」
第Ⅳ章では、これからの新しい“法”学習のあり方について考察されている。
本書は法教育関連の書籍としては初期のものではあるが、“法”に関する授業がいまだに本書にいう従来型の授業にとどまってしまいがちな状況に変わりはないと思われるところであって、本書の有用性はいまだ失われていない。
これから法教育に触れるという方においても、既に法教育に携わっているものの法教育の根本に立ち返って整理したいという方においても、有用な書籍である。
【主要目次】
まえがき
第Ⅰ章 “法”の学習はどうあるべきか?
1 社会科教育学者からの提案-市民が社会を構築する“法”学習の可能性
(1) はじめに
(2) 市民が社会を構築する“法”の学習の素描
(3) 授業1:現行法の実際(現実);法機能を理解する
(4) 授業2:法原理を理解する
(5) 授業3:法を反省的に理解したり吟味したりする
(6) 授業4:法を批判する
(7) 授業5:紛争(トラブル)を解決する
(8) 授業6:社会に参加する
(9) おわりに
2 法曹関係者からの提案-身近な問題を原理原則から考える学習の必要性
(1) はじめに
(2) 「何が」教えられるべきか
(3) 「どのように」教えられるべきか
(4) まとめ
第Ⅱ章 社会科における“法”の授業
1 “法”関係のニュースを扱う授業
(1) 裁判員制度
(2) 個人情報保護法-個人情報保護とプライバシー
(3) ロースクール
2 “法”を理解し“法”を反省する授業
(1) 中学校の事例-地理的分野「イスラームからみた日本の刑法」
(2) 中学校の事例-歴史的分野「ケンカ両成敗って正しい?~封建時代の法について考える~」
3 “法”を理解するとともに“法”を批判する授業
(1) 高等学校の事例-法的論争問題 少年法の授業
(2) 高等学校の事例-法的論争問題 外国人参政権の授業
第Ⅲ章 関連教科における“法”の授業
1 “紛争”を解決する授業
(1) 小学校中学年の事例-何が公平・不公平?
(2) 小学校高学年の事例-「責任」って何だろう?
(3) 中学校の事例1-ペナルティを考える
(4) 中学校の事例2-キャプテンを決めよう
2 社会に参加し提案する授業
(1) 小学校の事例-町の問題を解決しよう「減らそう放置自転車大作戦!」
(2) 中学校の事例-マンション建設を変更する解決案をつくろう
第Ⅳ章 あらたな“法”授業
1 法教育はどのようにとらえられてきたか
2 法教育の学習機会
3 これからの法教育
以 上